早稲田大学の過去5年間(2014~2018)の入試結果をもとに、各学部・学科等における受験倍率をランキング形式でまとめました。
また、簡単な解説もつけましたので、志望先を迷っている場合は参考になるかと思います。
文系学部
※一般入試で数学と理科のいずれも必須でない学部。
一般入試(センター+一般方式を含む)の受験倍率ランキング
※特に表示のないものは一般入試。
| 順位 | 学部 | 学科等 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会科 | 10.7 | |
| 2 | 教育 | 教育-初等教育 | 9.9 |
| 3 | 商 | 9.7 | |
| 4 | 教育 | 教育-教育-教育心理 | 8.1 |
| 5 | 教育 | 教育-教育-生涯教育 | 8.0 |
| 5 | 人間科 | 人間情報 | 8.0 |
| 7 | 文化構想 | 7.9 | |
| 8 | 教育 | 教育-教育-教育学 | 7.7 |
| 8 | 人間科 | 人間環境科 | 7.7 |
| 10 | 文 | 7.5 | |
| 10 | 政治経済 | 経済 | 7.5 |
| 12 | 人間科 | 健康福祉科 | 7.0 |
| 12 | 政治経済 | 国際政治経済 | 7.0 |
| 12 | 教育 | 複合文化 | 7.0 |
| 15 | スポーツ | 6.8 | |
| 16 | 教育 | 社会科-社会科学 | 6.5 |
| 16 | 教育 | 社会科-地理歴史 | 6.5 |
| 18 | 教育 | 国語国文 | 6.3 |
| 19 | スポーツ | (センター+一般) | 6.2 |
| 19 | 政治経済 | 政治 | 6.2 |
| 21 | 文 | (センター+一般) | 5.1 |
| 22 | 法 | 4.9 | |
| 23 | 教育 | 英語英文 | 4.7 |
| 24 | 国際教養 | 4.3 | |
| 25 | 文化構想 | (センター+一般) | 3.9 |
| 26 | 文化構想※ | (英語4技能) | 3.6 |
| 27 | 文※ | (英語4技能) | 3.3 |
※直近2年間(2017~2018)の平均値。
センター利用(個別試験なし)の受験倍率ランキング
| 順位 | 学部 | 学科等 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人間科 | 人間環境科 | 6.6 |
| 2 | 人間科 | 人間情報科 | 6.5 |
| 3 | 商 | 6.1 | |
| 4 | 文化構想※ | 6.0 | |
| 5 | 政治経済 | 経済 | 5.8 |
| 6 | 国際教養 | 5.6 | |
| 7 | 文※ | 5.1 | |
| 8 | 社会科 | 4.8 | |
| 9 | スポーツ | 4.5 | |
| 10 | 法 | 4.2 | |
| 11 | 政治経済 | 政治 | 4.1 |
| 12 | 人間科 | 健康福祉科 | 3.8 |
| 12 | 政治経済 | 国際政治経済 | 3.8 |
| 14 | スポーツ | (競技歴) | 3.5 |
※4: 直近3年間(2016~2018)の平均値。
理系学部(人間科学部の数学選抜方式を含む)
※一般入試で数学と理科のいずれかまたは両方を必須とする学部。
一般入試(人間科学部の数学選抜方式を含む)の受験倍率ランキング
※特に表示のないものは一般入試。
| 順位 | 学部 | 学科等 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育 | 理-地球科学 | 7.1 |
| 2 | 基幹理工 | 学系Ⅲ | 5.5 |
| 2 | 教育 | 理-生物学 | 5.5 |
| 2 | 創造理工 | 建築 | 5.5 |
| 5 | 教育 | 数 | 5.2 |
| 6 | 先進理工 | 生命医科 | 4.8 |
| 7 | 創造理工 | 経営システム工 | 4.7 |
| 8 | 基幹理工 | 学系Ⅱ | 4.2 |
| 8 | 創造理工 | 総合機械工 | 4.2 |
| 8 | 創造理工 | 社会環境工 | 4.2 |
| 11 | 先進理工 | 物理 | 4.1 |
| 12 | 先進理工 | 応用化 | 3.9 |
| 13 | 先進理工 | 電気・情報生命工 | 3.8 |
| 14 | 先進理工 | 化学・生命化 | 3.6 |
| 15 | 人間科 | (数学選抜) | 3.4 |
| 15 | 人間科 | (数学選抜) | 3.4 |
| 15 | 創造理工 | 環境資源工 | 3.4 |
| 18 | 人間科 | (数学選抜) | 3.1 |
| 19 | 基幹理工 | 学系Ⅰ | 3.0 |
| 20 | 先進理工 | 応用物理 | 2.8 |
| ― | 教育 | 理-地球科学(地学枠) | ― |
過去問を持とう
過去問といえば大定番の赤本。必ず自分専用のものを1冊持ちましょう。
青本も持とう
記述問題があるなら、解答例は多いに越したことはありません。赤本の解答例と比較対照することで、新たな視点とより深い理解が得られます。
参考書を揃えよう
早大受験生にお勧めの参考書はこちらです。
英語
国語
数学
日本史
世界史
その他
次によく読まれている記事
ここ1週間の間、この記事を読んだ人が次によく読んでいる上位記事はこちらです。
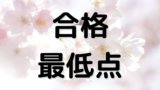
早稲田大学の合格最低点と倍率の推移【2006~2023】
早大の合格者成績と倍率の推移を最大17年分掲載。政治経済学部、法学部、文化構想学部、文学部、教育学部、商学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、社会科学部、人間科学部、スポーツ科学部、国際教養学部についてまとめています。
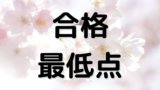
明治大学の合格最低点と倍率の推移【2006~2023】
明治大学の合格最低点を最大15年分掲載。法学部、商学部、政治経済学部、文学部、理工学部、農学部、経営学部、情報コミュニケーション学部、国際日本学部、総合数理学部についてまとめています。
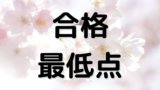
慶應義塾大学の合格最低点と倍率の推移【2006~2023】
慶応大学の合格者成績を最大17年分掲載。文学部、経済学部、法学部、商学部、医学部、理工学部、総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部、薬学部についてまとめています。









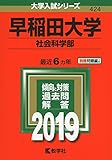























コメント